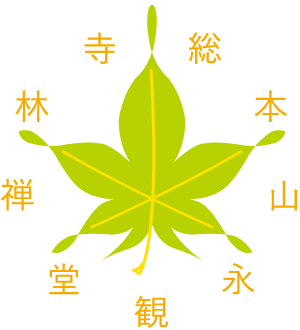【Creators Interview】限定夜間拝観「PureLand Lights」プロジェクションマッピング・アーティスト 三谷正さん
法然上人立教開宗850年記念事業にお力添えいただいた、さまざまなクリエイターのみなさんを紹介するインタビューシリーズ。第四回にご登場いただくのは、限定夜間拝観「PureLand Lights」において、『光の池上法要』と境内全体のプロジェクション・マッピングを含めた光の演出を担当した三谷正さんです。
永観堂境内の中心にある放生池の上に僧侶が立ち読経した『光の池上法要(いけうえほうよう)』、大殿に向かう参道や放生池を映し出した『光の浄土』そして、『光の池上法要』と地上創作舞台『法然上人と室津の遊女』のクライマックスに山に投影された『山越しの阿弥陀図』。PureLand Lightsは、現代の光の技術と僧侶によるコラボレーションによって創造された新しい法要になりました。
インタビューでは、三谷さんが永観堂という場所に積み重なってきた記憶、僧侶によって受け継がれてきた教えをどのように読み解き、立教開宗850年にふさわしい儀式をつくりあげていったのかを聞かせていただきました。
<プロフィール>
三谷正(みたに・ただし)
PiXelEngine LLC.代表。京都工芸繊維大学造形工学科卒業。大量のプロジェクターやスピーカーを用い、その場所のキャラクターを〈空間〉として当該地域に立ち上げる。福知山城、高台寺、舞鶴市赤レンガ倉庫郡、姫路城三ノ丸広場などのプロジェクション・マッピングを手掛けてきた。作品は、プロジェクター数十台、数百メートルの規模を採ることもあり、システム設計、3DCG制作などを自ら行う。
法然上人が「開いた」ことの意味を問う
ーー今回のプロジェクトはどんなふうにはじまったのですか?
三谷氏:「大殿に外から投影できないか」というお話もあったのですが、あまり面白くないし抵抗がありました。大殿内は面白い空間なんじゃないかと思い、実は試写までしました。なぜ面白いと思ったかというと儀式として成立する可能性があったからです。そこで、「850年の節目に新しい儀式をつくることに関われるのではないか」と考えはじめました。
大殿の中でやるとしたら、お客さん、演者、空間の自由がないことが僕のなかで引っかかりました。どうしたって劇空間的な演出になってしまう。でも、僕が本当にやりたいことは何なのかを考えて、1〜2週間かけて永観堂に通いました。僧侶のみなさんに教義や歴史について少しずつ聞かせていただき、僕なりに調べたりするなかで、大事なブレイクスルーがふたつありました。
ーーふたつのブレイクスルーについて教えてください。
三谷氏:850年前に法然さんがした「立教開宗」というのは、「はじめる」のではなく「開く」ということです。シンプルに言うと、「ポップにした」「パブリックなものにした」のだと理解しました。特権階級だけのものになっていた仏教を野に放つために、開いたのではないか、と考えたんです。
僕は、劇場空間や批評空間のような権力構造のなかにあるアートを、パブリックなところに持ち出す表現があってもいいはずだと考えています。お客さんには、見ることもできるし、見なくてもいいという自由な状態で作品を判断されたいんですね。そういう僕の考えと、法然さんがした「開く」はそんなに遠くないんじゃないかと思えたことが、最初のブレイクスルーになりました。
ふたつめのブレイクスルーは、境内を歩いているときに起きました。永観堂の立派なお庭で、庭師の方たちが膝をつき、手で小さな雑草を抜いて苔の手入れされているのを見てハッとしました。要するにこの空間には、素晴らしい環境を残すと「決めた」人がいて、それを実践している人たちの手が残っている。『光の参道』で両サイドの苔に光を当てたのは、石畳の道よりも、むしろ苔のほうに価値があると考えたからです。
すでに価値があるのだから、僕が表現として何かを投影するのではなく、ただそこが光ればいい。抽象的な価値や宗教観みたいなものを、空間として明示して具体化したいという思いがありました。僕がプロジェクターを使う理由もそこにあって、価値という抽象的な観念を、「ここに価値がある」「ここに境界がある」と明示できるからです。照明だけでは、境界を繊細にコントロールできませんから。

『光の参道』から放生池を見た瞬間の光景。ススキの美しさに息をのんだ。
場所に根付くトポロジーを読み解く
ーー『光の参道』の入り口に立った瞬間に、場所に対する敬意のある作品だなと感じました。いつもとは違う永観堂の夜だけれど、永観堂ではない場所になったわけではない。「いつもではない空間」を受け入れたことで感覚の変容が起き、見返り阿弥陀さまもいつもとは違うお姿に見えました。
三谷氏:要するにアートは感覚を変えるということです。アートは形式ではなく、自分のなかの「かっこいい」や「美しい」に1ページを付け加えるものだと思います。
ーーこれまでも姫路城や高台寺などで制作されていますが、やはりその場所を観察しながら読み解くことによって、受け継がれてきた価値を見出して表現してこられたのでしょうか。
三谷氏:今まさに言われたように、結局は一番インフォメーションが残っているのは場所なんです。まずは、過度にインフォメーションを入れずに、現地に行ってその場所に根付く歴史をトポロジー(位相幾何学)的に見るようにしています。この観点でいうと、城や寺においては庭の形や建造物のフォルムそのものが歴史ですから、「この道面白いな」「この建物はなぜこの形なんだろう」というところからはじめれば、自然と歴史に触れることになります。
歴史は解釈次第でどうにでもできる側面もあります。歴史にこじつけて「このアートが必要だ」と言うことだってできるかもしれません。でも、僕はそういうやり方には価値を見出していません。今回は、まずは僧侶の方たちに一番納得してもらえるかたちをすごく考えました。もともと場所がもっている価値と共存しながら、その良さを引き立てつつプラスの価値を加えて、1+1が3にも4にもならなければ、やる意味がないと思っていました。
ーー今回は、僧侶のみなさんとの対話の時間も多くもたれたと伺いました。
三谷氏:僕は、その場にとって正解に一番近いイメージが出ればいいと思っているので、現場にいる人たちとのディスカッションは大切にしています。だからできるだけ現場に足を運んで、そこにいる人たちの話を聞きます。そこで聞いたちょっとした会話から、必ず次のアイデアが出てくるんです。
「僕のキャリブレーション(映像の調整)は世界一」という三谷さんが3日間かけて仕上げたプロジェクション・マッピングは非常にクリアで美しい。(動画撮影・編集/西光院 藤賀多聞、音楽・MIX/近藤忠)
宗教における最大の価値は「僧侶」だと思った
ーー『光の池上法要』で、僧侶のみなさんに池の上に立ってもらうように提案したのは三谷さんだったそうですね。
三谷氏:最初のプレゼンから提案していました。僕のなかでは、僧侶のみなさんに池の上に立っていただくことが一番大きな仕事だったと言っても過言ではありません。先ほど、トポロジー的に場所から歴史を読み解くと言いましたが、僧侶と宗教も同じ関係性にあると言えます。
宗教の本質は「教え」ですよね。ただ、1940年代以降に電信が普及して以来、「教え」そのものが大衆化していきました。近年で言えば、YouTuberが「これがいい」「これを買いなさい」というのも、ECサイトなどのユーザーによるおすすめレビューも、自分の価値観をパブリックに発信するという意味では「教え」です。その結果として、世界中に玉石混交の教えが蔓延したがゆえに、「教え」そのものが形骸化しはじめている。大衆化の当然の帰結でもあります。
では、何百万人もフォロワーがいるインフルエンサーと僧侶は何が違うのかというと、先ほど言った「決めた」ということだと思います。YouTuberは流行らなくなれば辞めるかもしれませんが、僧侶の方たちは「この教えのもとで生きていく」と決めた人たちです。そこに迫力を感じるから、僕たちは畏敬の念をもち尊敬の眼差しを向けるわけですよね。そういうことを考えていたら、「宗教がもつ最大の価値は僧侶である」と思い至りました。
だから、立教開宗850年に新しい時代の儀式では、「教え」よりも「僧侶」にフォーカスを当てるべきだと思いました。僧侶を軸にして素晴らしい状態をつくれば儀式と成立するだろうし、2023年の僧侶による法要として語り継がれるだろう。そして、何よりも僧侶のみなさんの気持ちが残るだろうと思いました。いろんなことを考えた結果、最も僧侶が美しく見える、最も広くて開かれた場所は放生池しかなかったんです。
ーー放生池は大きな池です。池に灯体を大量に投入して、プロジェクション・マッピングを行うのは大変だったのではないでしょうか。

「僕のキャリブレーション(映像の調整)は世界一」という三谷さんが3日間かけて仕上げたプロジェクション・マッピングは非常にクリアで美しい。
三谷氏:一年半前に実験を行い、今回のプロジェクトに誘ってくださった中川龍学さんと若い僧侶の方たちに池の上に立っていただいて写真を撮った瞬間に「絶対いける!」と思いました。僧侶が立つ美しく幻想的な池、しかも宗教儀式として行うというアイデアは100%間違っていないと確信しました。国内では比類するものがないくらいに、クオリティの高いものができるという実感があったのです。
その時点で、作品の強度に対する心配はなくなり、逆に絶対にいいものができるのだから最後までこぼさないように運ばなければいけないというプレッシャーに変わりました。ゼロベースから立ち上げたし、正しいプロセスを踏んでいけば、おかしなことには絶対にならない。これはめっちゃキツいけど絶対に池でやろうと思いましたね。
ーー僧侶のみなさんが池に浮かんでいるようで、読経される姿はこの世ならぬものにすら見えました。お浄土に近いイメージもあったかもしれません。
三谷氏:いろんな意味があったと思います。極楽浄土として見ることもできたでしょうし。僕が好きなのは、僧侶たちの姿が水鏡に映ることによって、上下の観念の転換が起きていたこと。権力構造の逆転が起きるイメージもあって、すごく自由ですよね。たぶん、法然さんもその時代の仏教が息苦しかったんじゃないかなと、僕は思いたかったですね。

PureLand Lightsで使用されたプロジェクターは『光の参道』に37、放生池に9、山越しの阿弥陀像に3(合計49)。スタッフは総勢10名で投影した。
僧侶たちに熱望された「山越しの阿弥陀像」
ーー『光の池上法要』『法然上人と室津の遊女』では、クライマックスに『山越しの阿弥陀図』を山に投影されましたね。
三谷氏:実は、僕は基本的に具象的なものを投影しないんです。『光の池上法要』で、等高線のように線を投影しましたが、面ではなく線で空間を切ることによって、いつも見ているパースペクティブよりも立体感が強調されていたと思います。それによって、見る人の立体感に対する感受性を触りにいく。僧侶の姿が映像によって池に映ったり、切られたりすることによって、僕たちが「僧侶」「山」「庭」と強固に思い今でいるものが、一瞬ただ美しい凸凹になるという変異の方が絶対に面白いと思っているからです。

『山越しの阿弥陀図』に関しては、僧侶のみなさんからの熱望が凄くて(笑)。僧侶のみなさんが阿弥陀仏を礼拝し、讃えるお経(礼讃)「三尊礼(さんぞんらい)」を詠んでいるときに投影することにしました。結果的に、『山越しの阿弥陀図』は儀式として考えるならとても意味があるのだと、逆に僧侶のみなさんに教えていただいたと思っています。すごく喜んでくださいましたね。
ーー僧侶のみなさんの呼ぶ声に応じて、阿弥陀さまのお姿が現れたということですね。
三谷氏:僕はその気がなかったのに、僧侶のみなさんが願う力で阿弥陀さまが来てくださって儀式として完成したわけです。教義を捉えている僧侶のみなさんが望むかたちで実現したと意味でも、立教開宗850年にふさわしいものになったと思います。しかも、永観堂以外では絶対に見ることができない、唯一無二のものになりました。
『光の池上法要』のようす。僧侶の姿が変化するなか変わらぬ読経が響き、やがて『山越しの阿弥陀図』が出現する。(動画撮影・編集/西光院藤賀多聞、音楽・MIX/近藤忠)
ーー『光の池上法要』では、光によって僧侶のみなさんの姿が変容するなかで、読経の声だけは変わらない響きで聞こえてきて。むしろ、読経が主役になっているとも感じました。
三谷氏:その通りです。僧侶のみなさんが日頃修練されている読経の声は、教えを伝えることに特化して受け継がれてきた響きだと思います。出仕する僧侶の方たちは、「みなさんにお経を聞いてほしい」という思いから、相談しあって声のキーを合わせたりされていました。僕は、みなさんがしっかり声を出して読経してくださるだけで感動して泣きそうになりましたね。
ーー当初は7人の予定だったのに、希望者が増えて8人の僧侶が池の上に立たれたと伺いました。
三谷氏:最初はイメージが湧かなかったようですが、初日を終えてみなさんの雰囲気が変わったのを感じました。僕もホッとして「オッケー、オッケー」と思えたと同時に、全員に対して感謝しました。池の上に立ってくださった僧侶の方たち、この場を提供してくださった方たち、うちのスタッフたち。中川龍学さんとの偶然の出会い、法然さんの立教開宗850年というタイミングで、儀式というものにチャレンジさせてくれたすべてに感謝しました。
ーー足掛け3年対峙してきた永観堂のことを、今はどんなふうに感じていますか。
三谷氏:いろんな人、いろんな歴史や力がつくっている、必然性のある場所なんだと感じました。だから魅力的なんだと思います。いろんな要素が混ざり合っていて今も生きているから。僕にとっては、地形から歴史を読み解き、僧侶という存在から教えを知るという、トポロジー的な自分の方法論が間違っていなかったという自信にもなりました。シンプルにしんどいことをちゃんとやっていけば必ず結果が出る。場所としての価値が本当にあるのであれば、必ず面白い結果が返ってくると改めて思いました。
その価値は、僧侶のみなさん、檀家のみなさん、庭師の方たちなど、永観堂という場にいるすべての人たちがつくっているものだと思います。おそらく僧侶の方たちは、「現代において何をすべきか」を葛藤されていると思います。そんななかで、いろんな議論をして新しい儀式を生み出せたことは、めちゃくちゃ意味があったと思っています。
ーーありがとうございました。また次の作品を見せていただくことを楽しみにしています。
(取材・文・撮影、杉本恭子)