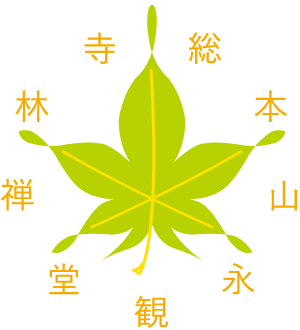【Creators Interview】池上創作舞台『法然上人と室津の遊女』能楽師 安田登さん
法然上人立教開宗850年記念事業にお力添えいただいた、さまざまなクリエイターのみなさんを紹介するインタビューシリーズ。最終回は、限定夜間拝観「PureLand Lights」において、池上創作舞台『法然上人と室津(むろつ)の遊女』を奉納された能楽師の安田登さんです。
『法然上人と室津の遊女』は、法然上人のエピソードに材を取った創作舞台。永観堂境内の中心にある放生池の上で、能楽師安田登の一座『ノボルーザ』と西山禅林寺派全国青年会のコラボレーションにより上演・奉納されました。また、雨天の日には大殿にて、法然上人像が見守るなかで演じられました。
インタビューには、教化伝道部の中川龍学さんも同席。安田さんの法然上人に対する関心、『ノボルーザ』による『法然上人と室津の遊女』の創作プロセスを中心に、さまざまなお話を聞かせていただきました。
<プロフィール>
安田登(やすだ・のぼる)
1956年千葉県⽣まれ。下掛宝⽣流ワキ⽅能楽師。元ロルファー。
⾼校時代、⿇雀をきっかけに甲⾻⽂字と中国古代哲学への関⼼に⽬覚める。⾼校教師時代に能と出会う。ワキ⽅の重鎮、鏑⽊岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で⼊⾨。現在は、能楽師のワキ⽅として国内外を問わず活躍するかたわら、『論語』などを学ぶ寺⼦屋「遊学塾」を東京を中⼼に全国各地で開催。⽇本と中国の古典の “⾝体性”を読み直す試みも継続。能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演も⾏なう。隣町珈琲でも「論語と⾝体」「古事記から探る⽇本⼈の古層」シリーズなど連続講座を多数開催。
池上で演じるなら「室津の遊女」がいい
ーー法然上人立教開宗850年にあたり『法然上人と室津の遊女』を上演されることになったのは?
安田氏:ちょうど「池上の法要」の試写が行われた日にたまたま京都にいたので、中川龍学さんに誘っていただいたんです。池の上に立つお坊さんたちを見て、『法然上人絵伝』のなかにある「室津の遊女」のエピソードがパッと思い浮かびました。
「室津の遊女」は、念仏弾圧の法難により四国へ流罪となった法然上人が、船で室津の沖(兵庫県)に差し掛かったとき、小舟に乗って教えを乞いにやってきた遊女に専修念仏を勧めるというお話です。今回の作品では『法然上人絵伝』をベースにアレンジしました。実は、法然上人の能は、30歳の頃にも書いたこともあるんです。
ーーということは、30歳の頃にはすでに法然上人に関心をおもちだったのですか。
安田氏:はい。関心をもった理由はふたつあります。ひとつは、浄土宗のお念仏は能によく出てくるんです。能は武士に愛された芸能です。そして、武士というのは人を殺めることをその職業としているので、本来は地獄に堕ちる可能性が高い。ところが法然上人は「お念仏さえ唱えれば誰でもお浄土に往生できるし、お浄土で修行すれば成仏できる」と教えました。それまでの仏教では、「人間を殺めているのに成仏できるはずがない」とされてきた武士にとって、その教えは驚くべき考え方だったんです。
もうひとつは、法然上人が日本でお念仏を発見したことです。空海や最澄は唐(中国)に留学して学んだ仏教を持ち帰って広めましたが、法然上人は日本にいながらにして専修念仏の教えに到達しています。ある意味で、これは日本人のための仏教だと思っていました。
しかも、僕の実家は、祖父の代までの姓は「魚躬(うおのみ)」という網元の家系です。やはり魚を殺すという殺生をするので、戦前までは一族の誰かが僧侶になったそうです。殺生をなりわいとする家系に生まれたこともあり、法然上人の教えにすごく惹かれました。
「遊女のままで救われる」という教えの魅力
PureLand Lights 池上創作舞台『法然上人と室津の遊女』ダイジェスト映像
ーー『法然上人と室津の遊女』のエピソードにどんな魅力を感じていましたか。
安田氏:やはり、「遊女がそのまま救われる」ことがとても魅力的でした。「罪業深き身」であっても、そのまま救われるといいます。最初は法然上人も「遊女をやめなさい」と言われるのですが、遊女たちが「この業捨つること叶ふまじ」と答えると、「遊女のままでいいから念仏を申しなさい」と説かれます。今回の上演では、ともに念仏を申していると、遊女たちは観音菩薩、勢至菩薩となって舞いはじめる、としました。そして、菩薩たちは「阿弥陀如来はあのお山に」と西の山を指差す。そこに現れた阿弥陀様を拝した法然上人は「皆ひと往生疑いなし」と随喜の涙を流しながら、配流先の讃岐の国に向かわれる、そのような物語にしました。
この教えは現代にも通じると思うんです。「本当はこんなことをしてはいけないんだけど」と思いながらも、やらざるをえないことはあります。わかっちゃいるけど、やめられないということもある。どうしようもない。でも、この「どうしようもない」というのが人生だと思うのです。そのとき、その人を責めても仕方ない。それでは一時的な解決にしかならない。だって、本人だってわかっているのですから。で、その「どうしようもない」問題を解決するときに、それまで誰も考えてもいなかったような全く別の矢印を入れてしまった。それがお念仏であり、このエピソードだと思うのです。
このような「どうしようもない」問題は現代社会にもよくあります。そこに「全く別の矢印」を入れることの大切さを教えてくれる、そんなエピソードだと思います。



ーー「別の何かになる」のではなく、そのままでいて救われることができるということですね。
安田氏:「遊女をやめる」というのではなくね。でも、これは「あるがままでいい」というのは違うと思います。ダメだとわかっていながら、どうしようもできない。そういう葛藤の中で苦しんでいる人を救ってくれるのがお念仏だと思うのです。今回は、お話の内容をわかってほしいのでナレーターを入れました。当初は、ストーリーを書いたパンフレットを配布するという案もありましたが、ナレーションによってよりお話を理解しながら観てもらえたのではないかと思います。
3時間前に決まった大殿での上演
ーー私が伺った日は雨だったので、池上ではなく大殿で観させていただきました。
中川氏:もともとは雨天中止の予定だったのですが、「なんとかならないか」という話になって。大殿の廊下部分での上演も検討したのですが、最終的には教学部長のご英断で大殿のなかで上演していただきました。大殿内での上演はお話がより際立ちましたし、中央には法然上人像がいらっしゃることも我々としてはすごくいい舞台だなと思っていました。

安田氏:大殿でやらせていただけたことはとても特別で、みなすごく感動しました。やはり、法然上人像があるところですから特別感がすごいんです。思わず法然上人に一礼し、それから演じはじめました。
実は、「大殿内でやる」と決まったのは上演の3時間前でした。会場が変わるわけですから、動きも変わる。詞章も変えました。直前になって、今までの稽古とは違う動きやセリフに突然変えたわけですが、ノボルーザのメンバーは動じない。むしろ楽しんじゃう人たちばかりです。キーボードのヲノサトルさんは、何か問題が起きるたびに「面白くなってきたぜ」と言っています。
ノボルーザのメンバーは、能楽師は僕だけで、あとは他の芸術や芸能の携わる人、あるいは本業を別に持っている人たちです。しかも「良い加減」の人たちが多い。稽古の時間が守れなかったり、楽器を忘れてきちゃったりね(笑)。もともと、いとうせいこうさんがつけてくれた名前は「登一座」だったのですが、ヲノサトルさんが「ラテン系だからノボルーザにしよう」と言って名前を変えたくらいです。
ーー本業が忙しい方が多いなか、みなさんとはどんなふうにお稽古をされているんですか?

安田氏:台本を渡して、まずは僕が謡って、みんなに謡ってもらいます。それから基本の動きを示して、あとは自分で考えてもらいます。稽古のときは、その人がもっとも力を発揮できるような勘どころを探して、そこを刺激するだけです。相手の流れを感じて、詰まっているところを外すようなイメージです。
中川氏:池の上ではお稽古できないし大丈夫かなと思っていたのですが、不安を感じさせない舞台でした。
安田氏:ノボルーザのみんなは堂々とするのが得意なんです。「気分でアドリブしてもいいよ」とも言っています。それぞれが場に応じてやっているので、音楽がいつどこで入ってくるのかなども事前に決めません。
ーー配役はどのように決められているんですか?
安田氏:これはやりながら決めました。船頭をひとりにするか、ふたりにするかも決まっていませんでした。ただ、セリフが多いとストレスがかかって自由に演じてもらえないので、一番セリフが多い役は僕が演じています。
「奉納」にご利益を求めてはいけない
ーー永観堂という舞台で演じたご感想を伺ってみたいです。
安田氏:水上の舞台は初めてでしたが、池の上でしか見えない景色があって、すごくよかったです。両方の橋が真ん中から見えたりして。

インタビューは中川龍学さんが住職をつとめる瑞泉寺にて行われました
中川氏:メンバーに自由に演じてもらうなかで、「違うな」と思うことはないんですか。
安田氏:たまにあります。たとえば、みんなが完璧に合わせようとするときなどは「合わせないほうがいい」と言いました。だって、みんなが完璧に合うのはマスゲームみたいで気持ち悪いし、一人ひとりが小さくなってしまうんです。特に人数が少ない場合はそれぞれが「自分はこの場を仕切るぞ!」と思いながらやるほうが絶対面白くなります。昔の人はもっと自由でした。今の人の方が合わせようとしすぎて不自由になっていると思います。
今回、ノボルーザの出演者は3分の1の人たちは自腹で出演しました。東京からの交通費も、宿泊費も自腹です。残りの3分の2の人たちの分は僕が出しました。自腹で出演した人たちは奉納だという気持ちで出演してれくました。これがノボルーザのいいところです。しかも「奉納したからいいことが起きるのではないか」なんていうご利益のようなことは誰も期待していない。「AをしたからBになる」という考え方に慣れすぎているけれど、そういう考えは誰も持っていない。だって神仏にギブアンドテイクを求めるのは変でしょう?
中川氏:永観堂という場自体が、みなさんを迎え入れている感じがありました。試写の日に、安田さんが偶然京都にいらっしゃったこと含め、いろんな偶然が重なって奉納していただけたのだなと思います。
長く続いてきたものは常に変化してきた
ーーお能という歴史ある伝統芸能を身に受け継いでおられる安田さんは、法然上人の立教開宗850年という長い歴史の節目をどのように受け止められたのでしょうか。
安田氏:伝統と古典には大きな違いがあります。古典は変化しませんが、伝統は「変化しないために変化すること」が重要です。たとえば能は、江戸時代と現代ではまったく違うと言われていますし、僕が若い頃と今でもずいぶん変化しました。そういう意味では、長く続いてきたものは常に変化してきたんじゃないかと思うんです。
今という時代は変化を求められている時代だと思います。そのときに、何を変化させて、何を変化させてはいけないのかを頭で考えてはいけない。人間の頭なんてたいしたことないし、考えるとつまらなくなっちゃう。ほうっておいても変化するものはするし、しないものはしない。流れに任せるのがいいんじゃないかと思います。変化は「起こす」というよりも、自ずから「起こる」ものなんですよ。
ーーたとえばお能では何が変化してきたのですか?
安田氏:すごくわかりやすいのはスピードです。たとえば、江戸時代初期の能は今の3倍くらいのスピードだったと言われています。
ーー時代のスピードは速くなっているように見えるのに、逆に遅くなっていったのはなぜでしょうか。

安田氏:たとえば、昭和初期の演説を聞くと口調が早いでしょ。今の国会議員はゆっくり話しています。頭で考えちゃうと「時代が速くなっているから、能も速くなっているんじゃないか」と思っちゃうけれど、それはあまり関係ないと思います。
ーー最後に、今回の作品をつくるにあたって、永観堂というお寺をじっくりご覧になって印象に残ったことを聞かせてください。
安田氏:作品をつくる前、中川さんに永観堂を案内していただいたとき、西山証空上人の和歌を教えていただき素晴らしいと思いました。「生きて身を 蓮(はちす)の上に宿さずば 念佛申す甲斐やなからん」。死んでから浄土に行くだけでなく生きているときにこそ、とおっしゃる。「まさにその通り」と思い、『法然上人と室津の遊女』でも地謡の一節に取り入れました。
ーーありがとうございました。これからも安田さんとノボルーザのみなさんのご活躍を楽しみにしております。
(取材・文・撮影、杉本恭子)